バーチャル・マニュファクチャリング
2001年5月 / 220号 / 発行:2001年5月1日
目次
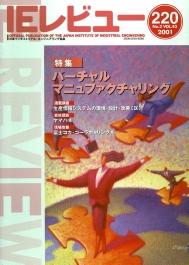
-
巻頭言
デジタルマニュファクチャリングによるモノづくりの変革をめざして
-
特集テーマのねらい(特集記事)
バーチャル・マニュファクチャリング
-
論壇(特集記事)
バーチャル・マニュファクチャリングの効用と課題
-
ケース・スタディ(特集記事)
バーチャルリアリティによるワイヤーハーネス組立検討
-
ケース・スタディ(特集記事)
バーチャル・マニュファクチャリングへの挑戦
-
ケース・スタディ(特集記事)
人体モデルによる住宅設備設計事例
-
ケース・スタディ(特集記事)
シミュレーション技術を活用したAPS運用システムの開発
-
ケース・スタディ(特集記事)
半導体・液晶工場のシミュレーションによる最適化
-
テクニカル・ノート(特集記事)
サイバー・コンカレントマネジメントの概念とフィールドファクトリ事例研究による仮想生産情報システムの構築
-
プリズム(特集記事)
有料道路料金所渋滞を緩和する21世紀の交通インフラ
-
プリズム(特集記事)
オープンロボット用通信インターフェース(ORiN)の開発と現状
-
プリズム(特集記事)
3次元CADの製造への適用可能性と課題
-
講座
生産情報システムの環境・設計・改善[Ⅸ]
-
会社探訪
工業製品としてのバイオリンをつくる-ヤマハ(株)-
-
現場改善
改善活動でモノづくりに感動を
-
コラム(15)
-
オーストラリア便り(2)
-
協会ニュース
-
新製品紹介
-
新刊紹介
-
編集後記
はじめに
バーチャル・マニュファクチャリングという言葉は、一過性の流行語に過ぎないかもしれない。なぜなら、バーチャル(仮想〉で実際の物を作れるはずがないという意味で、この言葉はそもそも奇妙だからである。しかし、この言葉はIT時代の生産システムの改善にふさわしい多くのヒントを、我々に与えてくれるような気がする。どのようなヒントを与えてくれるだろうか。そのためには、バーチャル・マニュファクチャリングの意味を考えることが必要であろう。
バーチャル・マニュファクチャリングとは
バーチャル・マニュファクチャリングの意味を考えるためには、その親戚の概念ともいえるバーチャル・オフィスとかバーチャル・カンパニーを引き合いに出して論じることが、近道であるように思われる。
-
バーチャル・オフィス、バーチャル・カンパニー
数年前からバーチャルリアリティ(仮想現実)という言葉が流行ってきた。それにともなって「バーチャル・オフィス」「バーチャル・カンパニー」などという言葉が出てきた。これらの言葉が意味するところは、コンピュータを使用して、コンピュータと人間の頭のなかに仮想のオフィスや会社を作成する、そして、それを関連する人々に共有させ、実際の仕事を仮想空間上で行っていく、というようなことだと考えられる。たとえば、バーチャル・オフィスは、実際に事務室や机、椅子などを設置し、そこに事務員を一堂に会して仕事をする、というようなことをしなくても、仮想空間上に事務室や事務員などを想定し、実際のオフィスワークができるようにした空間のことをいうと思われる。 -
バーチャル・マニュファクチャリングとバーチャル・オフィスの相違点
バーチャル・マニュファクチャリングも同様に、工場を設置しなくても、仮想空間上で物を生産できるというイメージかと一見思われる。しかし、バーチャル・マニュファクチャリングでは、実際には物を製造できない。それに対してバーチャル・オフィスでは、ある程度現実的な仕事はできる。それは、オフィスは物を作っているわけではなく、多くの場合情報を作っているからである。それに対してバーチャル・マニュファクチャリングは、物を作ることができない。それなのに、なぜバーチャル・マニュファクチャリングという言葉が生まれたかというと、工場でもオフィスワークに近い作業があり、それを仮想の世界でこなすことができるからである。たとえば、部品や製品の設計はバーチャル・オフィスと同様に仮想の空間でかなりできる作業である。このようなことから、バーチャル・マニュファクチャリングという言葉ができ、それを使用しても特に違和感を感じられなくなってきたのではないかと考えることができる。 -
工場におけるバーチャル
では、工場におけるバーチャル作業としてどんなものが考えられるだろうか。その典型は、前述したように設計作業である。工場における設計作業は部品や製品の設計だけに限らない。それ以外に、例えば、次のようなものがある。
工程設計
人間の作業・動作の設計
工程設計では、従来は実際の模型や現実の設備などを使用して、工程を設計してきた。しかし仮想空間を作成して、模型も設備も3次元で表現し、コンピュータのなかで工程を設計していくことが可能になってきた。同様に、人間の動作を3次元で表現し、コンピュータのなかで、楽で能率的な動作による作業のシステムをあらかじめ設計しておくことができると思われる。ところで、生産管理における「スケジューリング」や「在庫管理」も、ある意味では設計作業に入る。スケジューリングでは、現在のデータを使用して、今後どのようなスケジュールで作業を進めていくべきかを臨機応変に計画していくことができれば、これもバーチャルの作業と言えなくないように思われる。在庫管理も、現在のデータを使用して、何を・いつ・いくつ発注または生産すればよいかをコンピュータのなかでリアルタイムに計算していけば、バーチャルといえなくはない。実際、スケジューリングや在庫管理は、すでにバーチャルで行われつつある。それはシミュレーションである。これらのシミュレーションは、ある意味ではバーチャルリアリティかもしれない。ここで、シミュレーションとバーチャルの違いが問題となってくる。 -
バーチャルとシミュレーションの違い
私の考えでは、バーチャルのスケジューリングとは、いま現在の工場の稼働状況の実際データを使用して、その時・その場でのスケジュールをダイナミックに作成していくことだと考える。つまり仮想空間上でスケジューリングを行うためにシミュレーションを行う、というのが、シミュレーションとバーチャルの関係であると考える。従来のシミュレーションは、あくまでも実験にとどまる。それに対してバーチャルは、実際の仕事を処理していくことである。また、従来のシミュレーションは、数字ばかりが並ぶ、いわばデジタルの世界である。それに対してバーチャルは、3次元図に代表されるように、アナログの世界をめざしているようにも思われる。つまりバーチャルは、より人間に理解されやすいようにしてある。そうする理由は、臨場感を増すためと、実際にすぐに使えるようにするためである。さらに、シミュレーションは最適化を追求するのに対して、バーチャルではそれほど最適化にこだわらない。バーチャルでは最適化よりも実行性に意義があるように思われる。 -
バーチャル・マニュファクチャリングの定義
これらをまとめて、筆者なりに定義すると、「バーチャル・マニュファクチャリングとは、
リアルタイム性(即時性)
可視化
リアリティ(臨場感)
実行性
などを重視して、時間と距離の短縮化による効果をめざし、コンピュータを使用して頭のなかに仮想空間を作って、生産に関わる実際作業を行っていくこと」ということができる。
バーチャル・マニュファクチャリングのIEにおける応用分野
上の定義を踏まえて、工場の機能の観点からバーチャルのIEにおける応用分野を考えると、次のように整理できる。
- ●設計
製品設計
工程設計
レイアウト設計
人間の作業の設計 - ●生産管理
スケジューリング
在庫管理 - ●生産作業
作業指示(実際の生産作業をバーチャル画面を見ながら、それを真似して行っていけるようにしたもの) - ●物流・運搬
実際に物理的な変化を加える必要がないのに移動していた物についてはバーチャル化する。
たとえば、分類とか整理は物理的に物を移動させる必要は必ずしもないので、それを仮想空間上で行う。 - ●教育
バーチャルリアリティを使用して、より現実的で臨場感ある教育を行う。
おわりに
今回の特集号では、ここで述べた考えに基づいて、バーチャル・マニュファクチャリングの詳しい解説や事例を掲載するように努めた。多分に設計や技術に偏りがちなテーマを、できるだけ製造に近い立場から考察しようと考えてケースを依頼した。今後に向けた改善のヒントを、本特集号から発想して頂けることを願っている。
黒須 誠治/編集委員

