日本の「モノづくり人材」
2004年10月 / 237号 / 発行:2004年10月1日
目次
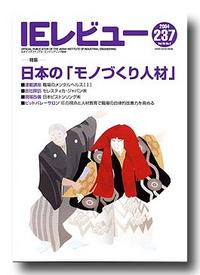
-
巻頭言
モノづくりは人づくり
-
特集テーマのねらい(特集記事)
日本の「モノづくり人材」
-
論壇(特集記事)
わが国製造業の現状と製造現場の中核的人材の強化の必要性
-
ケース・スタディ(特集記事)
「モノづくり=人づくり」を実践する現場経営塾「5ゲン道場」
-
ケース・スタディ(特集記事)
ゼロから出発した技能伝承への実践的な取り組み
-
ケース・スタディ(特集記事)
「日本発モノづくり企業」をめざして
-
ケース・スタディ(特集記事)
PCM法による経験に依存しない生産体制の確立
-
ケース・スタディ(特集記事)
人が育てば会社が変わる
-
テクニカル・ノート(特集記事)
改正された労働派遣法の解説
-
インタビュー(特集記事)
日本の伝統工芸文化を継承するモノづくり人材の育成
-
プリズム(特集記事)
モノづくりのまち大田区における地域人材育成
-
プリズム(特集記事)
技能五輪への取り組み
-
プリズム(特集記事)
ものづくりを支えるマイスター制度
-
連載講座
職場のメンタルヘルス[Ⅰ]
-
会社探訪
日本型ハイエンドEMSをめざして-セレスティカ・ジャパン(株)-
-
現場改善
インジェクター部品外観検査の改善による疲労蓄積軽減と生産性向上
-
ビットバレーサロン
IEの視点と人材教育で職場の自律的改善力を高める
-
コラム(32)
-
アメリカ便り(1)
-
協会ニュース
-
新刊紹介
-
編集後記
モノづくりを支える「モノづくり人材」
枯渇の恐れと求められる新しい人材像
まず、量の課題は、企業のリストラ、業務のアウトソーシング、生産の海外へのシフト、そして少子高齢化ということから発生する「人材確保難」である。リストラやアウトソーシングによる人員削減や、海外への生産展開を進めるなかで人材の採用に消極的となっていることもあり、「モノづくり人材」の確保が難しくなっている。また、団塊の世代がモノづくり現場を去り始める時が、数年後に迫ってきている。つい一昔前までは、若い意欲的人材が補充され、優秀なモノづくり人材に育て上げられてきた。しかし、少子化が進み労働力人口が減り始めたなかで、若者の製造業離れが顕著になり、モノづくりに関わりたいという若者は少数派になっている。このような情勢は、モノづくりの優れた人材を育成し、確保することを従来に比べ困難にしている。手をこまねいていれば「モノづくり人材」が枯渇する恐れがある。
質の課題は、国際的な競争が激化するなかで、日本のモノづくりをさらに洗練化し、他国に追随を許さないモノづくり競争力を確保する必要から発生している。海外に生産を展開すると、どうしても日本のモノづくりのノウハウが多かれ少なかれ流出して行く。日本のモノづくりを学ぶことにより、海外のモノづくりのレベルは毎年上がってきている。数年前には、海外ではできないと思われてきた商品の品質がいつのまにか確保されてきている。競争力を維持するためには、一歩進んだモノづくりを実現し続けなければならない。そのために、「モノづくり人材」に求められている人材像が広がっている。単なる技能者、生産管理マンではなく、技能者であると同時に、機会保全もやり、生産管理などのマネジメントもこなす「モノづくり人材」の従来の分担の枠を超えた多能工化が簡素で効率的なモノづくりには必要である。従来以上に「モノづくり人材」の質の高度化とモノづくりの新しい人材像が求められている。モノづくり人材の獲得と高度化への育成は、企業経営の最重要課題のひとつであることは間違いない。
特集テーマの切り口
特集記事について
-
論壇
経済産業省産業人材参事官室の白戸恒彦氏にわが国製造業を支える人材の課題と、それに対応するために計画されている新しい人材育成システムについて論じていただいた。熟練された技術・技能の伝承が危惧され、かつ、よりさらに高度な技術・技能が求められている。しかし、企業が社内プログラムで高度な技術・技能を持つ人材を育成・確保することは困難になっている。そこで、2005年度から経済産業省が計画している「産学連携製造中核人材育成事業」について述べられている。 -
ケース・スタディ
- ①クボタ/現場経営塾である「5ゲン道場」について紹介していただいた。同社ではTPI活動と言う「5ゲン主義」に基づいた生産革新活動を推進している。その活動の核となる人材を育成するために「5ゲン道場」は開設された。正しい知識を得る「座学」、座学で学んだことを実際にやってみる「実習」、そして自職場に戻って改革を行う「実践」の3つのステップを、踏んでいる。まさに「5ゲン主義」をDNAとする鍛錬の場になっている。
- ②日東電工/経営トップと人事部門、製造部門が一体となって築いた「技能塾」について紹介していただいた。知識と実践に基づく「技能塾」の構築にいたるステップとその人材育成のシステムと「技能士」制度について述べられている。「技能士特級」から「技能士3級」までのレベルがあり、その認定条件は明確になっている。’03年度までに633名の「技能士」が誕生している。
- ③NECトーキン/モノづくりのスピードを速くするために展開されている「超生産革新」活動を通じたモノづくり人材育成について紹介いただいた。外部コンサルタントによるトレーナー養成講座に始まり、社内の改善実践会とその報告会、そして、「社内改善マン養成講座」を開設している。理論と実践の両面から教育し、従業員の10%がトレーナーもしくは改善マンとなって改善活動をリードしている。
- ④TORAY Plastics(America)/離職率の高い米国で、個人の経験に頼らなくてすむ管理システムとして、PCMシステムを導入し、生産能力の大幅な改善を成し遂げた事例を紹介いただいた。PCMシステムは0から4までの5つのレベルに分けて推進され、モノづくり人材が持っている経験の暗黙値を形式値にして行った。形式値となった経験をもとに、オペレータの技能習熟を短期かつ確実に行っている。
- ⑤住友電工/ラインカンパニー制という現場に日々損益がわかるシステムを導入し、社員を単なるサラリーマンではない経営と言う視点を持たせることで、人材育成と体質改善を推進している事例を紹介していただいた。経営意識を醸成するために、KLCスクールで経営に関する知識を植え付け、それを実際に職場で実践させることでモノづくり人材の育成・強化を行っている。
-
テクニカル・ノート
労働者派遣法が改正され、製造業務にも派遣が解禁され、モノづくり人材の確保にも影響が予想される。日本人材派遣協会の加藤高敏氏に製造業への派遣について法のポイントを解説していただいた。 -
インタビュー
北海道札幌市の千秋庵製菓会長で、千秋庵製菓短期大学校校長の岡部卓司氏に、インタビューをお願いした。全国でも珍しい和菓子の短期大学校設立の動機、教育内容、苦労話、卒業生の活躍をお聞きした。トップとしての熱意が伝わってくる。 -
プリズム
まず、モノづくりのまち大田区のテクノクリエター推進、モノづくり見聞録の発行、高校生のインターンシップによるモノづくり体験など、多彩な活動を大田区産業振興協会から紹介していただいた。次に、技能五輪全国大会、そして、国際大会へのチャレンジを通じて、世界トップレベルの技能集団の養成している状況をデンソー技研センターに紹介していただいた。最後に、伝承すべき技能を峻別し、その技能を保持する技能者をマイスターとして認定・登録し、技能を伝承している制度を不二越に紹介していただいた。

