国内生産と海外生産のすみわけ
2004年12月 / 238号 / 発行:2004年12月1日
目次
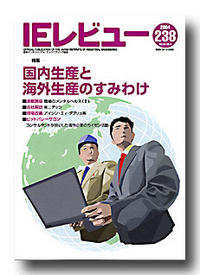
-
巻頭言
グローバルな視点での海外進出と国内生産の取り組み
-
特集テーマのねらい(特集記事)
国内生産と海外生産のすみわけ
-
論壇(特集記事)
国内生産と海外生産のすみわけ
-
ケース・スタディ(特集記事)
トヨタのグローバル生産の現状と課題
-
ケース・スタディ(特集記事)
「made by Japan」でのものつくり(技術融合型ものつくり)をめざして
-
ケース・スタディ(特集記事)
海外進出と市場ニーズに対応した工作機械作り
-
ケース・スタディ(特集記事)
国内生産にこだわる富士通のパソコン製造法
-
ケース・スタディ(特集記事)
「7日間即納活動」で見えてきた国内生き残りの道
-
論考(特集記事)
技の伝承と人づくり
-
レポート(特集記事)
平成15年度ものづくり白書(製造基盤白書)
-
プリズム(特集記事)
海外展開と今治タオル産地の空洞化
-
プリズム(特集記事)
製造業が真に国内回帰するための課題とは
-
プリズム(特集記事)
近未来の中国と日本の産業
-
連載講座
職場のメンタルヘルス[Ⅱ]
-
会社探訪
世界に挑戦した愚直なモノづくり-(株)ニデック-
-
現場改善
無動力搬送台車「ドリームキャリー」の考案・製作
-
ビットバレーサロン
コンサルタントが目にした海外企業のカイゼン活動
-
研究論文
生産ライン効率化のための累積流量図とガントチャートの活用
-
コラム(33)
-
アメリカ便り(2)
-
協会ニュース
-
新刊紹介
-
編集後記
特集テーマのねらい
新聞や専門誌の報道を見ていると、多少の不確実さや見解の相違はあるものの、民間設備投資の増勢が続き、製造業復活の兆しは着実に進みつつあるように見受けられる。経済産業省が発表したものづくり白書も、その表題が「攻めに転ずるわが国製造業の新たな挑戦と製造基盤の強化」となっており、「国内に工場は残らない」とされてきた数年前とは状況が一変している。その背景には、いわゆる「デジタル景気」と「中国景気」があるといわれている。薄型テレビ受信機・DVDレコーダー・デジタルカメラ・カメラつき携帯電話など、デジタル家電の売れ行きが好調で、エルピーダメモリや松下電器産業などが相次いで新工場建設を行い、デジタル家電関連の日本国内主要メーカー24社の設備投資額をみると、2003年度は2002年度に比べて7割増の1兆2,000億円に達している。直近では、富士写真フイルムが液晶部品の新工場建設を発表するなど、その動きは加速されている。また、相変わらず新工場やインフラ整備で建設ラッシュに沸く中国向けの輸出が好調である。工作機械メーカーへの波及効果も大きく、工作機械の受注額は2004年2月の時点で17か月連続で毎年同月比プラスとなっている。しかし、こうした動きの背景を見てみると、生産革新などの活動に力を注いで国内生産の活性化に進んでいる企業、国内での人件費やインフラコストの高さから海外生産比率を高めている企業、部品調達や製品物流面でのリスクと技術流出の点から国内と海外の使い分けを正面から考えている企業など、様々な方向が指向され混在しているのが実情である。そこで、上記のように経済全体の動きが「製造業復活」の方向へ流れ出した今こそ、真の意味で「国内生産と海外生産のすみわけ」はいかにあるべきかを考えてみようというのが、今回の特集のテーマの背景である。一般に、電気・ガスなどのエネルギーコスト、法人税、地価、規制業種の横持ちコスト、人件費などの高コスト構造が、日本での国内立地を難しいものにしていると言われている。しかし、その一方で、市場の近くで作ることにより、流通を含めたリードタイムを短縮できるので、物理的なコスト以外の要素も含めた「トータルコスト」の見方をすることが大切であるとも言われる。このように考えると、物理的なコストをいかに克服し、国内で立地することにいかなるメリットを見出しているのかを明らかにすることが必要になる。グローバルという立場からは、「国内」と「海外」を二律背反的に分けて捉えることに既に意味がないと考えることもできるが、海外工場から国内へ回帰している工場も見られるなかで、今一度、国内に立地することの意味とメリットを考えてみたいのである。このことが、本特集の第1のねらいである。第2のねらいは、管理技術という視点である。国内でのモノづくりを考えるとき、試作・立ち上げ的な使命に力点を置き、固有技術力の観点から製品・技術のあり方を考える場面は多いが、競争優位を保つためには、固有技術での優位性と管理技術での優位性という両方の側面がある。本来、どうやって造るかということが日本の製造業の強みであったはずである。本誌の使命として、IE、QC、PMなど、国内でのモノづくりを支える管理技術の優位性と今後の課題を深耕することが、この特集の第2のねらいである。以上をまとめると、上記の2点に着目したケースの紹介を通じて、日本でつくることのメリットを、海外とのすみわけという視点で改めて考えることが、今回のねらいである。
記事の編成
上記のねらいに沿って、本号では、以下の論壇1件、ケース・スタディ5件、論考1件、レポート1件、プリズム3件の記事を掲載している。主な内容を要約しておこう。
-
論壇
本号の企画チーム主担当を務めた産能大学の斎藤文が、「国内生産と海外生産のすみわけ」と題して、執筆している。国内製造業の空洞化や海外生産比率の増加のデータ、その一方で国内工場建設の事例などを引用しながら、海外と対比して国内でモノづくりを行うことのメリットと課題を、生産技術、供給体制、管理技術という3つの視点から論じている。
-
ケース・スタディ
トヨタ自動車の安形哲夫氏には「トヨタのグローバル生産の現状と課題」と題して、グローバル生産のなかでの日本生産車と日本でのモノづくり、人づくりの現状を紹介して頂いた。特に、販売変動に対応するために、海外工場と国内工場で同じ車種を生産し、変動に対して国内工場で対応することで海外工場の稼働を安定させる「ブリッジ生産」の取り組みは、一定以上の生産規模が前提になるものの、海外生産と国内生産のすみわけ・両立を考えていく上で示唆に富んだ内容である。参入障壁が高いと言われる自動車産業でもモノづくりの総合力で世界の一歩先を歩むべく、究極のリーン生産とベスト技能を育成すべきという主張も、改めてモノづくりの原点を考えさせてくれる視点である。ブラザー工業の皆方克夫氏と村上泰三氏には、「『made by Japan』でのものつくり(技術融合型ものつくり)をめざして」と題して、工場用ミシン事業を例として、同社の中国進出の歴史を要約して頂いた。3段階に分けて歴史をまとめて頂いていること、第1段階では中国への量産品移行にともなって国内で多種少量品の生産効率が上がった点、第2段階ではFMSラインを改造して中国へ移設し、日本ではコンカレント化に注力して競争力を高めた点、第3段階では高速加工ラインを中国向けに開発導入している点など、技術に踏み込んだ海外進出のあり方を的確に紹介して頂き、その上で日本でのモノづくりの方向性を考察されている点で、迫力あるケースとなっている。「made in Japan」から「made by Japan」というメッセージも、大切なキーワードである。ヤマザキマザックの小坂秀人氏には、「海外進出と市場ニーズに対応した工作機械作り」と題して、ITツールを活用してゼロから海外工場を立ち上げた経験をべ一スに、海外工場運営の特徴と日本工場とのすみわけについて、紹介して頂いた。特に、機種別の国際生産分業の中での日本工場の位置づけには、他の業種でも参考になる知見が要約されている。島根富士通の山田壽男氏には、「国内生産にこだわる富士通のパソコン製造法」と題して、PC生産における国内生産のメリットを、Q・C・Dに分けて紹介して頂いた。特に、不良ゼロヘの取り組み、コスト削減に向けた生産革新、セルを活用したスピード供給は、決して新しいことではないとしても、国内生産を位置づける大切な視点である。エクセディの内田朗仁氏には、「『7日間即納活動』で見えてきた国内生き残りの道」と題して、徹底したリードタイム短縮により国内での体質強化に取り組んできた内容を紹介して頂いた。工程分析から出発し、能力増に向けた工程と生産管理の改善、品質不良対策、設計との協業など、地道な改善プロセスの紹介は大変に迫力がある。究極のリードタイムで世界に負けないモノづくりというメッセージは、我々の多くに元気を与えてくれるものである。
-
論考
また、本特集に対する論考として、名古屋工業大学大学院教授・ものづくりセンター長の藤本英雄先生に「技の伝承と人づくり」と題して寄稿をお願いした。国内モノづくりに関する産官学の最先端の活動を紹介頂いた上で、日本のモノづくりの強さを再考するための4つの視点を提示頂いている。社会の動きと合わせて日本のモノづくりの将来を展望する上で、具体的な視点が事例と共に論述されており、改めて海外生産とのすみわけを考える上で、基本的な視座を示して頂いている。 -
レポート
本号では、経済産業省の水口伸平氏に、「平成15年度ものづくり白書(製造基盤白書)」の要約をレポートとして執筆頂いた。日本メーカーの中国での事業展開や国内生産回帰の動きをデータを事例に基づき解説した上で、国内製造業活性化のポイントが、企業間連携や抜本的プロセス革新の視点から具体的に論じられている。 -
プリズム
最後に、特集テーマに沿ったプリズムとして、本号では転入品に対抗し、高付加価値品の開発で伝統産業活性化に取り組んでいる四国タオル工業組合の事例、持続可能な競争力という視点から国内生産のひとつの方向を論じた日本政策投資銀行の小論、補完関係とFTAという視点で日中間の生産分業を論じた野村資本市場研究所の小論という3件を掲載している。
河野 宏和/編集委員長、斎藤 文・篠田 心治/企画担当編集委員
【論壇】国内生産と海外生産のすみわけ
本号の企画チーム主担当を務めた産能大学の斎藤文が、「国内生産と海外生産のすみわけ」と題して、執筆している。国内製造業の空洞化や海外生産比率の増加のデータ、その一方で国内工場建設の事例などを引用しながら、海外と対比して国内でモノづくりを行うことのメリットと課題を、生産技術、供給体制、管理技術という3つの視点から論じている。
【ケース・スタディ】トヨタのグローバル生産の現状と課題
トヨタ自動車の安形哲夫氏には「トヨタのグローバル生産の現状と課題」と題して、グローバル生産のなかでの日本生産車と日本でのモノづくり、人づくりの現状を紹介して頂いた。特に、販売変動に対応するために、海外工場と国内工場で同じ車種を生産し、変動に対して国内工場で対応することで海外工場の稼働を安定させる「ブリッジ生産」の取り組みは、一定以上の生産規模が前提になるものの、海外生産と国内生産のすみわけ・両立を考えていく上で示唆に富んだ内容である。参入障壁が高いと言われる自動車産業でもモノづくりの総合力で世界の一歩先を歩むべく、究極のリーン生産とベスト技能を育成すべきという主張も、改めてモノづくりの原点を考えさせてくれる視点である。
【ケース・スタディ】『made by Japan』でのものつくり(技術融合型ものつくり)をめざして
ブラザー工業の皆方克夫氏と村上泰三氏には、「『made by Japan』でのものつくり(技術融合型ものつくり)をめざして」と題して、工場用ミシン事業を例として、同社の中国進出の歴史を要約して頂いた。3段階に分けて歴史をまとめて頂いていること、第1段階では中国への量産品移行にともなって国内で多種少量品の生産効率が上がった点、第2段階ではFMSラインを改造して中国へ移設し、日本ではコンカレント化に注力して競争力を高めた点、第3段階では高速加工ラインを中国向けに開発導入している点など、技術に踏み込んだ海外進出のあり方を的確に紹介して頂き、その上で日本でのモノづくりの方向性を考察されている点で、迫力あるケースとなっている。「made in Japan」から「made by Japan」というメッセージも、大切なキーワードである。
【ケース・スタディ】海外進出と市場ニーズに対応した工作機械作り
ヤマザキマザックの小坂秀人氏には、「海外進出と市場ニーズに対応した工作機械作り」と題して、ITツールを活用してゼロから海外工場を立ち上げた経験をべ一スに、海外工場運営の特徴と日本工場とのすみわけについて、紹介して頂いた。特に、機種別の国際生産分業の中での日本工場の位置づけには、他の業種でも参考になる知見が要約されている。
【ケース・スタディ】国内生産にこだわる富士通のパソコン製造法
島根富士通の山田壽男氏には、「国内生産にこだわる富士通のパソコン製造法」と題して、PC生産における国内生産のメリットを、Q・C・Dに分けて紹介して頂いた。特に、不良ゼロヘの取り組み、コスト削減に向けた生産革新、セルを活用したスピード供給は、決して新しいことではないとしても、国内生産を位置づける大切な視点である。
【ケース・スタディ】『7日間即納活動』で見えてきた国内生き残りの道
エクセディの内田朗仁氏には、「『7日間即納活動』で見えてきた国内生き残りの道」と題して、徹底したリードタイム短縮により国内での体質強化に取り組んできた内容を紹介して頂いた。工程分析から出発し、能力増に向けた工程と生産管理の改善、品質不良対策、設計との協業など、地道な改善プロセスの紹介は大変に迫力がある。究極のリードタイムで世界に負けないモノづくりというメッセージは、我々の多くに元気を与えてくれるものである。
【論考】技の伝承と人づくり
本特集に対する論考として、名古屋工業大学大学院教授・ものづくりセンター長の藤本英雄先生に「技の伝承と人づくり」と題して寄稿をお願いした。国内モノづくりに関する産官学の最先端の活動を紹介頂いた上で、日本のモノづくりの強さを再考するための4つの視点を提示頂いている。社会の動きと合わせて日本のモノづくりの将来を展望する上で、具体的な視点が事例と共に論述されており、改めて海外生産とのすみわけを考える上で、基本的な視座を示して頂いている。
【レポート】平成15年度ものづくり白書(製造基盤白書)
経済産業省の水口伸平氏に、「平成15年度ものづくり白書(製造基盤白書)」の要約をレポートとして執筆頂いた。日本メーカーの中国での事業展開や国内生産回帰の動きをデータを事例に基づき解説した上で、国内製造業活性化のポイントが、企業間連携や抜本的プロセス革新の視点から具体的に論じられている。
【プリズム】海外展開と今治タオル産地の空洞化/【プリズム】製造業が真に国内回帰するための課題とは/【プリズム】近未来の中国と日本の産業
特集テーマに沿ったプリズムとして、本号では転入品に対抗し、高付加価値品の開発で伝統産業活性化に取り組んでいる四国タオル工業組合の事例、持続可能な競争力という視点から国内生産のひとつの方向を論じた日本政策投資銀行の小論、補完関係とFTAという視点で日中間の生産分業を論じた野村資本市場研究所の小論という3件を掲載している。

